【M&A小説】資本か、経営か Vol.1
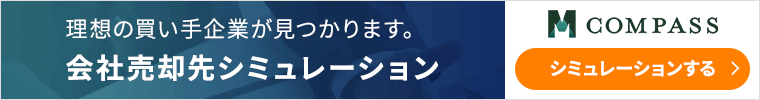
⽬次
- 1. 著者
※お断り※ この小説では、当社社員は実在する人物ですが、その他の登場人物や企業名はすべて仮名あるいは架空です。
M&Aの現場で日々戦うM&Aコンサルタントの目を通して、資本と経営の間で揺れ動く売り手オーナーの機微、M&Aにおける買い手企業の意思決定の裏舞台、M&Aコンサルタントの仕事の醍醐味など、M&Aの現場のリアルを描写する連載小説。

プロローグ
「あんたか、俺の会社を売り飛ばそうってのは」
開口一番、角井が耳にした言葉だ。
クリニカル商事子会社の吉川パーツは、医療機械器具の部品製造を営んでいる。
その社長室でのできごとだ。
日本M&Aセンターの角井は、東証一部に上場するクリニカル商事本社からグループ内再編(資源の集中や効率化を目的に、子会社の切り離しや買収を行う)の依頼を受けたM&A仲介のプロコンサルタントである。
2019年のこの日、吉川パーツの創業社長・吉川と初めて対峙することになったのだ。
何も知らない吉川からすれば、先の反応は当然のことだろう。この仕事をしているとよくある誤解だ。この誤解を解くことから、角井の仕事は始まる。
「ちがいます。あなたの会社を成長させるためのお手伝いをしに来たんです」
「会社を売ること、M&A自体を否定的に取らないでください。吉川さんのこれまでのご苦労を理解し、これからの発展に向けて寄り添っていくパートナーを見つけたいんです」
2019年は、吉川パーツとその創業社長である吉川にとって、運命の年となる。
吉川の章 クリニカル商事との対峙
ここまでくるには、もちろん紆余曲折があった。
「会社を売れというんですか?!」
親会社からの呼び出しを受け、クリニカル商事本社の経営企画担当から話を聞いた吉川は、一瞬目の前が暗くなった。
「会社を創って、ここまで大きくしてきたのは自分です!確かに私は資本をもっていません。株主はあなた方です。でもだからといって・・・納得できません」
吉川パーツは、吉川が資本金1000万円をクリニカル商事から出資してもらい、2003年に創業した会社である。クリニカル商事のいち商社マンであった吉川は、担当していた医療業界がきっかけで起業した。医療機器製造に携わる 人々の、人体に対する精緻な真摯さに打たれ、医療機器部品を専門に製作する会社を創業することになった。
そこに、クリニカル商事が出資金を援助した形で、吉川パーツが船出したのだ。
最初から順調だったわけではない。しかし商社で鍛えられた営業力と創業者としての重責をバネに売り上げを伸ばし、13年目となる2019年には、従業員も50名を超えた。
現在は、主に医療機器部品の製造と一部販売まで手を広げている。
その矢先、親会社がグループ子会社を再編するという。
自分はどうなるのか?いやそれよりも社員はどうなるのか。
資本か、経営か。
協力関係としてしか見ていなかった相手が、いきなり反目する相手に見えてくる。
M&Aコンサルタントの角井と対面したのは、これらの思いでざわつく胸中を、目まぐるしい日々の社長業で紛らわせていた最中だった。
遠山の章 選択と集中戦略は待ったなし
2019年初頭、角井はクリニカル商事の経営企画室・遠山と会っていた。
M&A業務は通常、大企業であれば経営企画が担当する業務となる。業務提携や資本提携、様々なアライアンスを実践していくのが経営企画だからだ。
「知っての通り、クリニカル商事はグループ会社の選択と集中戦略を取っています」
「上場企業なら、時代に即した事業展開をするためにグループを最適化するのは当たり前のことですね」
上場企業の選択と集中戦略は、待ったなしだ。
上場企業は多くの場合買い手となるが、日本のM&Aの歴史ももう長い。現状のコアビジネスに対して合わなくなっている事業が必ず出てくる。またどのような目的で、誰が買ったのかわからなくなっているグループ会社もある。
そのような場合は、グループから切り離すために売る、という判断になる。さらに、次の事業の柱も、M&Aで手に入れないとスピードが追いつかない。それを繰り返して新陳代謝を促すことで、持続的な成長を維持するのだ。
上場企業であっても安泰はない時代、競争は熾烈だ。
「その一環で、今回売却が決定した企業で吉川パーツという会社があります。社長はクリニカル商事の商社マンだった人物ですが、クリニカル商事からわずかな資金援助を受け起業した、気骨のある人物です」
「なるほど。その会社の相手探しをしてくれる仲介会社を探していると」
「はい。今回、日本M&Aセンターに仲介会社の社内コンペに入っていただきたいと思っています。参加される気はありませんか?」
「ぜひ。このディールは、私たちしかできないと思います」
昨今、M&Aを実施していない上場企業は皆無に等しい。毎日、どこかの企業がM&Aを発表しているのが現状なのだ。


