買い手にとってのM&A。目的や留意点とは?
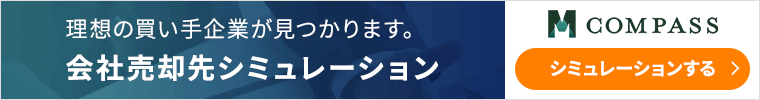
買い手の買収戦略には様々な目的があります。M&Aの成功に向けて、押さえておきたいポイントを確認していきましょう。
この記事のポイント
- 買い手がM&Aを行う目的には、市場シェアの拡大、事業領域の拡大、事業の多角化、人材獲得・技術力向上、効率性の向上がある。
- 買収により、企業は迅速に成長を加速し、顧客ベースや販売チャネルを拡大することができる。
- M&Aにはコストや中長期的な取り組みが必要で、成約後の経営統合計画を綿密に立てて実行することが重要である。
⽬次
- 1. M&Aの目的①市場シェアの拡大
- 2. M&Aの目的②事業領域の拡大
- 3. M&Aの目的③事業の多角化・新規事業参入
- 4. M&Aの目的④人材獲得・技術力向上
- 5. M&Aの目的⑤効率性の向上
- 6. M&Aを行う際の留意点
- 6-1. コスト(対価・費用)をあらかじめ認識しておく
- 6-2. 中長期で取り組む覚悟が必要
- 7. おわりに
- 7-1. 著者
M&Aの目的①市場シェアの拡大
企業は競合他社を買収することで、自社の市場シェアを拡大することができます。これにより、企業は競争力を高め、市場での地位を強化することができます。市場シェアの拡大により、企業は購買力の向上や交渉力の強化が可能になります。
また、同業の会社であれば商流が非常に似通っているため、企業間での仕入れ、発注費用の統合、企業間の手数料や販管費削減などにより、コスト削減が実現できるケースも多く存在します。
M&Aの目的②事業領域の拡大
既存事業の強化という点では、同業の会社を譲り受ける選択肢のほか、関連する事業分野の企業を譲り受けることも有効です。
例えば、戸建建築事業者が、土地造成業者とM&Aを行うと想定します。
これまでは、営業をして、自社で土地を仕入れ、建築を実施していたとしても、多くの場合で造成等は外部の会社にアウトソーシングしていたところを、自社グループに入ってもらうことで、グループ内に当該外注費を取り込め、品質、納期も守ることができる体制構築が可能となります。
また、メーカーが販路先である販売店を譲り受けるというケースも多くあります。販売店をグループ内に入れることで、メーカーは製造から販売まで一貫して事業を行うことができるようになります。
M&Aの目的③事業の多角化・新規事業参入
新規事業展開を行う際、一番有効でリスクが少ない手法としてM&Aが活用されるケースも増えています。事業を一つに集中させるのではなく、全く違う事業との二軸にすることで、リスク分散をさせることができるということが認知されはじめています。
2021年以降コロナ禍の影響を↑、飲食事業者、旅行事業者等、特定の事業者が、異業種に進出するケースも多く見受けられました。複数の事業を展開することで、特定の事業の業績が芳しくない状況になっても、別事業で補完する動きは今後も増加していくと考えられています。
また、M&Aによって新規事業を展開することで、自社で一から行うよりもスピーディーに立ち上げられます。買収する対象企業の従業員を一挙に確保できるだけではなく、その事業のノウハウなどもあわせて獲得できるためです。
M&Aの目的④人材獲得・技術力向上
特定の技術や資格を持つ人材を買収うるケースも増えています。これにより、企業は自社の製品やサービスの品質や競争力を向上させることができます。また、技術や知識の獲得により、企業は新たなイノベーションや研究開発の推進が可能になります。
昨今、日本の人口減少に伴い、多くの業種において人材を獲得する為のM&Aは活発化し,特に人材派遣、人材紹介会社のM&Aは年々件数が増加しています。
そのほか建設・建築業界や運送業界、調剤薬局、病院など、その業務内容と在籍者が保有する資格が業績や事業規模拡大に必要不可欠な業界では、有資格者を獲得する為のM&Aが頻繁に行われています。
また、こうした有資格者・技術者を取り込むことで、自社の今まで手掛けてこなかった分野、技術獲得を図るためM&Aが実行されるケースも増えています。
前述の業種の中でも、特に建築士や建築施工管理技士、土木施工管理技士等の有資格数に関しては、入札参加資格等にも影響しますので、非常にニーズが高まっていると言えるでしょう。また、ドライバー不足が続く運送業界においても、大型免許取得者や実務経験者の相対価値は高まっており、取引先や車両、配送拠点等を同時に取得できることからM&Aを通じた拡大を目指す企業は年々増えています。
また、資格者が密接に紐づいていない業界においても、技術力を獲得する為のM&Aも数多く起こっています。例えば製造業では、ある特定の技術を持つ人材、設備、機械装置がなければ製造・加工できないような製品を手掛けている企業をM&Aで取り込むことで、業界内で大きく競合優位性を獲得できるケースがあります。
M&Aの目的⑤効率性の向上
同業や関連事業会社とのM&Aでは、仕入れコストの削減、製造ノウハウの共有、物流面の連携、販売面の連携(クロスセル)などのバリューチェーンに着目したシナジー効果が生み出しやすいと言われています。
また、同業種、異業種であっても、信用力の向上による資金調達面や会計面でのシナジー効果をだすことも可能です。
人材のポストが増えることによるエンゲージメント強化や、採用強化など、一見すると、外からはわからない様なシナジー効果が生まれることも数多くあります。
人口減少、市場縮小が見込まれる現在、自社単体では成長性に限界を感じている企業は多く存在します。
買収は、以上のような目的実現し成長を加速化させる手段として活用されています。成長が見込める企業を買収することで、企業は前述のように市場拡大や新規事業の展開を迅速に行うことができます。
また、買収により企業は顧客ベースや販売チャネルを拡大することができ、成長を促進させることができます。
これらの目的を達成するために、企業はM&Aを戦略的に活用して他の企業を買収することがあります。ただし、M&Aはリスクも伴うため、買収する企業は事前に十分なデューデリジェンスを行い、買収の可行性やリターンを評価する必要があります。
M&Aを行う際の留意点
以上のように買い手はM&A通じて多くのことを期待できる一方、いくつか留意点もあります。
コスト(対価・費用)をあらかじめ認識しておく
M&Aにはお金がかかります。代表的なものは対象企業に支払う対価、M&A仲介会社の協力を得る場合は成功報酬、デューデリジェンスなどで専門家への報酬、登記等手続き費用などです。
全てを含めて「投資」としてとらえ、それに見合う「効果」が得られるか慎重に検討することをお勧めします。
中長期で取り組む覚悟が必要
M&Aの成立は相手ありきであるため、高い意欲を持っていても希望のタイミングで見つかるとは限りません。
また、M&Aは成約がゴールではなく実行後からが本番です。買収後の経営統合を含め、長期的な観点で準備・取り組む覚悟が必要になります。
「M&Aはお金で時間を買うようなものだ。0から新規事業を立ち上げるより時間を短縮できる。」という意見があります。それは間違いではありません。
しかし、歴史や社風の異なる企業同士の統合は一朝一夕でなしえません。M&A後のシナジーを発揮するには、経営統合計画を綿密に立てて実行に移しましょう。
おわりに
以上、買い手のM&Aの目的についてご紹介しました。
M&Aは自社の成長速度を高める有効な手段である反面、ご紹介した留意点をふまえ、目的を実現させるM&Aにそなえましょう。












