日本のM&Aの歴史
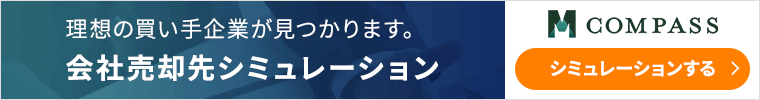
日本のM&A件数は年々増加しており、2019年に4,000件を超えて過去最高の水準となりました。今、なぜM&Aはこれほど増えているのでしょうか。また、今後M&Aはどのようになっていくのでしょうか。本記事ではM&Aの歴史をひもときながら、現状のM&A市場の理解、また将来のM&A市場についてお伝えしていきます。
※本記事は2021年9月28日に公開された内容を編集しています。
この記事のポイント
- M&Aの歴史は1980年代のバブル期に外国企業を買収する動きから始まり、1990年代には中小企業のM&A黎明期を迎えた。2000年代にはIT企業の台頭があり、M&Aの認知度が向上した。
- 2010年代には中小企業のM&Aが急成長し、後継者不在や業界再編型のM&Aが増加した。成長戦略としてのM&Aの活用も広がり、専門のM&A仲介会社が増加した。
- 2020年代は引き続きM&A件数が増加し、経営者の高齢化や黒字廃業の問題から中小企業M&Aの必要性が高まる。オンラインでのM&Aプラットフォームの利用も進展している。
⽬次
M&Aの歴史:バブル期に外国企業を買収(1980年代)

かつての日本企業では「企業を買収する」という発想は一般的ではありませんでした。1980年代に入り、バブル期においてクロスボーダー型のM&Aが活発に行われるようになりました。
当時の日本企業は好景気で、投資先として海外のリゾートホテルやマンションなどをこぞって買い漁っており、買う対象の一つに会社が入っているような感覚でした。
M&Aの代表的な例としては、映画「Stand By Me」などで知られる米国映画会社「コロンビア・ピクチャーズ・エンタテインメント」をソニーが買収した例があります。
ソニーは同社を親会社のコカ・コーラから約48億ドル(約6700億円)で買収しました。映画産業は、ハリウッドに代表されるようにアメリカを代表する産業の一つであり、文化においても重要な存在となっています。
ハードに強いソニーにとって映画会社を買収することは、ハードとソフトの両輪で事業を展開することができ、イメージしやすいシナジー効果がありました。しかし、アメリカの映画会社がジャパンマネーに買収されることは「魂を売った」と多くのアメリカのメディアで批判されることとなりました。
このように1980年代では、「M&A」といえば大企業がクロスボーダーで海外の企業を買うことを意味する、このような時代でした。
M&Aの歴史:失われた10年―中小企業M&A黎明期(1990年代)

バブルが崩壊し、「失われた10年」と言われる1990年代に突入します。
1991年4月25日、日本M&Aセンターが設立されました。当時、M&Aについて世間一般ではほとんど知られていない状況です。一方で、中小企業の間では経営権の承継が問題になりはじめていました。なぜなら、1980年代の頃から少子高齢化が急速に進展することは分かっており、事業承継問題が社会問題となることが予測できたためです。実際に後継者がいないがどうすればいいか、そんな相談を多くの会計事務所などに寄せられるようになりました。
しかし会社を譲渡することは、当時メディアでは「〇〇〇社が身売りに」「△△△社を乗っ取った」とネガティブに表現されていました。かつては終身雇用・年功序列が当たり前であり、いわば社員は家族も同然であったため、会社を譲渡することは家族を第三者に売るような感覚があったのかもしれません。M&Aの話が出ても「会社を売るなんてとんでもない」、そのような意見が大多数でした。
そのような中で創業当時からM&Aを取り扱っていた当社も、どちらかというと世間から警戒心を持たれている印象でした。当時、M&Aそのものの認知度が非常に低かったことも関係していたと考えられます。親族に「M&Aの仕事をしている」と伝えると「チョコレート会社で働いている」と似たブランド名のチョコレートと勘違いされたこともあったほど、当時はまだ認知がされていませんでした。
日本M&Aセンターは1991年4月創業、同6月に営業を開始し、1992年2月に第1号となるM&Aが成立しました。
これは東京都にある、とある業界のデータを打ち込む会社が譲渡企業(売り手)のお客様、譲受企業(買い手)は近隣におけるソフトウェアの会社でした。
日本M&Aセンターの中小企業の支援というスタンスは創業当初から変わっておりませんが、当時バブル崩壊のため景気が悪化しており、当社においても積極的な拡大戦略はとってこなかったため、中小企業のM&Aは一部でおこなわれているという状態が続きました。
M&Aの歴史:IT企業の台頭と中小企業M&Aの拡大(2000年代)

2000年代に入るとITバブルで株価は上昇し、M&Aの件数も拡大していきます。
M&Aがニュースでも取り上げられることも増え、一般的にも認知度が高まっていきます。有名なところでは、2005年にライブドアのニッポン放送株の買収事件があります。フジテレビの筆頭株主であるニッポン放送株に対し、新興IT企業であるライブドアが敵対的買収を仕掛けるといったものでした。既存メディアvs新興IT勢力という構図、過去にあまり例を見ない買収劇、日々変わる情勢に日本中が釘付けとなりました。毎日のようにテレビで報道があったため、当時のニュースを覚えてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
他にも村上ファンドのニュースが話題になるなど、M&Aそのものの知名度は高まっていきました。しかし、証券取引法違反の疑いで当時のライブドア代表が逮捕され、インサイダー取引の疑いでファンドの代表が逮捕されるなど、M&Aへの印象は悪化していきます。敵対的買収(対象企業の同意を得ないままに企業買収を進める方法)自体は、全体から見ればかなり稀なケースなのですが、「M&A=乗っ取り」「M&Aはこわい」といった印象が強まることとなりました。
2000年代当時の日本M&Aセンター
中小企業向けのM&Aに関しては黎明期が続いていましたが、実は日本M&Aセンターでは創業から10年たち、大きな転換点を迎えます。「このまま少人数のプロフェッショナル集団でいるか」それとも「拡大路線に舵を切り、事業承継を大きく進めていくか」です。この時、当社は後者を選択しました。
創業以来、当社はこれまでは全国の会計事務所様と提携しておりましたが、賛同いただける会計事務所様の数を増やすことも計画します。創業時には50だった提携会計事務所を、100まで増やすことを目指していきました。またこの頃から地域金融との提携もスタートします。人材に関しても、先行投資的に、採用を進めて人を増やす方向に転換していきました。
ただ、まだまだ中小企業のM&Aマーケットというものは確立されたものではなく、M&Aそのものはあまり認知されていない、あるいは悪いイメージが強い状態です。そのため連日のようにセミナーを開催してM&Aの良さを伝える啓発活動も進めていきました。
M&Aの歴史:M&Aの潮目の変化(2000年代後半)

マイナスの印象が広まったこともあり、なかなかM&Aが浸透しない状況でしたが、2006年にこの流れを替える一つの転換点を迎えます。中小企業庁から「事業承継ガイドライン」が策定・公表されました。これは、以下図にあるように、中小企業経営者の高齢化が進んでおり、20年間で経営者年齢が47歳から66歳に移動していく予測があります。次世代への円滑な事業承継の促進と、中小企業の事業活性化を図るため、中小企業庁がそのガイドラインを示したのです。
そのガイドラインの中では事業承継の方法として、(1)親族内承継、(2)役員・従業員承継、(3)社外への承継(M&A等)の3つに分類されています。
- 親族内承継・・・現経営者の子をはじめとした親族に承継させる方法です。
- 役員・従業員承継・・・「親族以外」である社長などの役員や従業員に承継する方法です。
- 社外への承継・・・株式譲渡や事業譲渡(M&A)で第三者に承継する方法です。
ここで重要な点は、「国が事業承継の手段として、M&Aという方法がある」ということを記載していることです。国が事業承継の方法として3つの選択肢を提示している中で(1)の親族、(2)の役員・従業員、を後継者にすることが難しい場合は(3)のM&Aによる第三者承継が残された選択肢になる、というのは非常に分かりやすく整理された考え方です。そして、国のガイドラインに沿っていることもあり、これまでの「M&Aへの悪い印象」から、「M&Aは事業承継の手段の一つ」として徐々に意識が変わっていくこととなりました。
なお、日本M&Aセンター(現 日本M&Aセンターホールディングス)は2006年10月にマザーズへ上場、2007年12月には東京証券取引所第一部へ市場を変更(2022年4月に東証PRIMEに変更)しております。東証一部上場企業が手掛ける、という点で顧客企業にとっても安心感が高まっていきました。
M&Aの歴史:M&Aの急成長フェーズ(2010年代)

2010年代、中小企業のM&Aは右肩上がりの「急成長フェーズ」に入りました。その件数はそれまでの10年と比べ、10倍近くの増加となりました。
「後継者不在」を解消するM&Aは当時最も多くありましたが、そのほか「業界再編型のM&A」や「成長戦略型のM&A」についても拡大傾向が見られました。
業界再編型のM&A
同業種の会社が手を取り合い、業界内で企業数が集約されていくM&Aになります。
身近な代表的な例としては、コンビニエンスストアが挙げられます。市場シェアはセブンイレブン・ローソン・ファミリーマート、が圧倒的に多く、大手で90%以上の市場シェアがあります。一昔前では、サークルKやサンクスなどもありましたが同社は、2016年にファミリーマートに経営統合されています。
中小企業向けのM&Aで代表的な業種としては調剤薬局があります。
成長戦略型のM&A
譲渡側(売り手)オーナーの年齢に関係なく、会社の成長のためにあえて会社を売るという選択肢をとることがあります。
M&Aは会社の成長戦略の方法として即効性があり、高い効果を期待できるものですが、買うのではなく実は売ることも成長の起爆剤になります。買うか売るのではなく、どこと組むのかを考える、それが「成長戦略型のM&A」です。
こうした形のM&Aが中小企業において活発になってきたのも、M&Aが経営戦略の一つの手法として浸透してきた証でしょう。
M&A仲介業でも中小企業のM&Aを専門に扱う会社も2000年代後半から徐々に増え始め、現在では大小合わせて300社とも400社ともいわれるほどです。1,2名の小規模な会社から、数百名の会社まで規模としても様々な会社が存在する業界となりました。
M&Aの歴史:中小企業M&Aの行方(2020年代)

今後の中小企業M&A業界はどうなっていくのでしょうか。
まず、引き続きM&A件数は増加していくものと予想されます。経営者の高齢化問題は深刻です。帝国データバンクによれば、2018年で経営者の年齢のピークが69歳となっています。そして、中小企業庁によれば経営者の引退時期は68歳から69歳と推察されており、引退の時期にかかってきています。また60歳以上の経営者においては約48.7%が後継者不在となっています。
一方で、日本では毎年約60,000社が黒字廃業していると言われています。約60,000社の黒字廃業に対し、中小企業M&Aの必要性は、今後増していくものと予想されます。
M&Aを取り扱っている会社については、増加傾向であることに加え、差別化が進んでいくでしょう。高付加価値のサービスを提供する会社、特定の業種に特化した会社、低価格で打ち出す会社など様々です。
また、昨今はオンラインでM&Aを完結させる動きも広がっております。例えば海外ではBizBuySell社、日本M&AセンターグループではBatonz(バトンズ)というオンラインM&Aプラットフォームの運営を行っています。
終わりに
以上、国内を中心にM&Aの歴史と、日本M&Aセンターの創業からの歩みを合わせてご紹介させていただきました。M&Aに対する、かつてのネガティブなイメージから、徐々に経営戦略の一つとして浸透していったことが伝わりましたら幸いです。








