M&Aの税務を専門家が解説
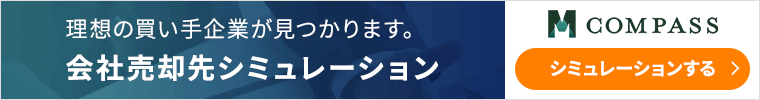
M&Aの税務知識はなぜ必要か?
中小企業のM&Aでは、想像以上の大きな対価で取引が行われることが少なくありません。その際に、採用するM&Aスキーム(手法)によって税負担や手取額が大きく異なるケースがあります。
譲渡オーナーがM&A後に引退する場合、M&Aによって獲得する対価はその後の人生の生活資金となります。さらに、子や孫に財産を多く残したいと考える場合、M&Aによる最終的な手取り額は非常に重要です。
買い手側では、M&A後に売り手企業の会社運営を続けていくことになります。税金を含む会社運営のコストを少しでも抑えたいと考える経営者が多い、と考えられます。
M&A税務の知識があれば、より有利な手法を採用し、売り手側であれば自らの財産をより多く残すことができる可能性があります。買い手側であれば、税金コストを適切に削減することで、その資金を更なる企業の発展に充てることが可能となります。
本記事では売り手、買い手双方が押さえておくべきM&A税務について、押さえておくべき基本事項を中心にご紹介します。
この記事のポイント
- 中小企業のM&Aでは、株式譲渡が多く用いられ、個人の株式譲渡に係る税率は20.315 %である。
- M&Aの成功には、理論的価値や相場を把握し、適切な投資判断基準を設定することが重要で、特に相場を反映した評価手法が求められる。
⽬次
- 1. M&Aの税務知識はなぜ必要か?
- 2. M&Aで発生する税金の種類一覧
- 3. M&A税務で売り手が検討すべき事項
- 4. M&A税務で買い手が検討すべき事項
- 5. M&A税務のポイント(株式譲渡の場合)
- 5-1. 株式譲渡の手続き
- 5-2. (1)株式の現物の有無の確認
- 5-3. (2)譲渡承認手続き
- 5-4. 株式譲渡に係る税金の計算過程
- 5-5. (1)株式譲渡所得の計算過程
- 5-6. (2)譲渡収入
- 5-7. (3)取得費
- 6. 売り手が留意すべき点(株式譲渡の場合)
- 6-1. 株式譲渡による所得の認識時点
- 6-2. 株式譲渡に係る税金の申告・納付時期
- 7. 買い手が留意すべき点(株式譲渡の場合)
- 7-1. 株式の取得価額として資産計上される価額
- 7-2. 中小企業事業再編投資損失準備金
- 8. M&A税務のポイント(事業譲渡の場合)
- 8-1. 事業譲渡の手続き
- 8-2. 事業譲渡に係る税金の計算過程
- 9. 売り手が留意すべき点(事業譲渡の場合)
- 9-1. 事業譲渡の実行時の課税
- 9-2. 事業譲渡に係る税率
- 9-3. 事業譲渡対価の還流時の課税
- 10. 買い手側が留意すべき点(事業譲渡の場合)
- 10-1. 税務上ののれん(資産調整勘定)の取扱い
- 10-2. 仲介手数料やDD費用などの諸経費の取扱い
- 10-3. 消費税の取扱い
- 11. M&A税務のポイント(退職金について)
- 11-1. 退職金の概要
- 11-2. 退職金支給の手続き
- 11-3. 退職金の支給額と税金の計算過程
- 12. 売り手が留意すべき点(退職金について)
- 12-1. 退職金を受け取るオーナー社長個人の留意点
- 12-2. 退職金を支払う売り手企業の留意点
- 13. 買い手が留意すべき点(退職金について)
- 13-1. 退職金の支給による損金算入
- 13-2. 退職金の支給による投資額の圧縮
- 14. M&A当事者にとって、税務の知識は不可欠
- 14-1. 著者
- 14-2. 監修
M&Aで発生する税金の種類一覧
中小企業のM&Aにおける税金は、株式を売却したときに発生する個人の所得税や住民税だけではありません。M&Aスキーム(手法)によって法人税や消費税、贈与税、相続税など、多岐にわたる税金の検討が必要になります。
※1 長期保有の不動産を前提としている
※2 不動産売買には別途流通税(不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税等)の検討が必要
M&A税務で売り手が検討すべき事項
譲渡オーナーが株式を売却した場合や、売り手企業が退職金を支給した場合には所得税(復興税を含む)と住民税が課税されます。
中小企業のM&Aで多く用いられるスキーム(手法)は株式譲渡ですが、案件によっては事業譲渡が用いられる場合もあります。
事業譲渡の場合は、売り手企業に法人税等が課されます。その他にも消費税や不動産取得税、登録免許税、印紙税などの流通税の検討が必要となるケースもあります。
さらに、組織再編を組み合わせたスキームや、M&A後の資産運用など、M&Aを検討するにあたっては様々なケースに対応できるよう、広範囲な税務の知識が求められます。
M&A税務で買い手が検討すべき事項
買い手側では、退職金や繰越欠損金をはじめ、M&A実行時だけでなく、M&A実行後、数年間の売り手企業における「税金計算に影響を及ぼす事項」についても検討を行います。
M&Aを機に譲渡オーナーが引退する場合の「役員退職金」や、売り手企業の繰越欠損金といった個別事項のみならず、スキーム毎に生じる税務上の論点まで多岐にわたります。
そのため中小企業のM&Aを検討する際には、売り手、買い手ともに幅の広い税務の知識が求められます。
M&A税務のポイント(株式譲渡の場合)

中小企業のM&Aのスキームでは、多くのケースで「株式譲渡」あるいは「事業譲渡」が用いられます。また、それらのスキームの実行の際に、「退職金」を併せて支給することも多く行われています。
様々なスキームのうち「株式譲渡」が多く用いられている理由は、他のスキームと比較して、売り手、買い手双方の立場から見てもメリットを多く享受できる傾向があるためです。

株式譲渡は、売り手企業の株主が所有する株式を買い手企業に譲渡するスキームです。
この株式譲渡は、会社を「丸ごと」譲り渡すことになります。基本的に株主構成の変化以外に、譲渡される会社自体に大きな変化は見られません。
株式譲渡は他のスキームに比べて手続きが比較的簡便であり、株式譲渡に係る税率は個人であれば一律20.315%です。
また、株式譲渡はM&A対価を売り手の株主が直接受け取れるスキームであるため、株主である譲渡オーナーの手取額が多くなりやすい手法といえます。
一方、株式譲渡では売り手企業が抱えるリスク(財務、税務、労務、法務など)を含めた権利義務の全てを買い手側がそのまま引き継ぐことになります。
そのため買い手側では、売り手企業の状況に応じてリスクの有無・重要性を事前に確認するためデューデリジェンス(買収監査)をしっかりと行う必要があります。
株式譲渡の手続き
売り手側の株主と買い手企業で株式譲渡契約を締結後、事前に定めた一定のクロージング条件を満たしたことを双方が確認します。
その上で、売り手側の株主が買い手企業に株式を引渡し、買い手企業はその対価を売り手側の株主に支払います。株式譲渡によるM&Aは、手続き面において比較的シンプルな手法といえます。
(1)株式の現物の有無の確認
買い手企業への株式の引渡しは、売り手企業が「株券発行会社」「株券不発行会社」かによって次のように異なります。
「株券発行会社」の場合は、実際に株券を買い手企業に引き渡す必要があります。
「株券不発行会社」の場合は、現物の株式の引き渡しは不要です。
平成18年会社法施行以降に設立された会社であれば、原則的には株式不発行会社に該当します。
それ以前に設立された会社であれば、実際に株式を発行している可能性があるため、現物の有無をしっかりと確認することが非常に重要です。
(2)譲渡承認手続き
多くの中堅・中小企業の株式は「譲渡制限付株式」に該当します。譲渡制限付株式の場合は、株主がその売り手企業の株式を会社の許可なく勝手に譲渡することはできません。
株式を譲渡する際には、会社に譲渡承認を受ける必要があるので、会社法に則った手続きを行う必要があります。
株式譲渡に係る税金の計算過程
株式譲渡における税金の計算過程も、手続きと同様シンプルな手法です。
(1)株式譲渡所得の計算過程
個人が株式を譲渡した際の税金は、株式の譲渡所得に所得税率15.315%(復興税を含む)と住民税5%の合計税率20.315%を乗じて計算されることになります。
所得税では、原則として累進課税が適用されますが、株式譲渡は税率が20.315%で固定されるので有利となる傾向があります。その株主の株式譲渡に係る税金は、以下の通り計算されます。

株式譲渡における税金は、株式譲渡で儲かった金額、含み益について税金が課されることになります。
もちろん含み益がなく、譲渡損が発生する場合には税金は発生しません。しかしながら、M&Aによる第三者への株式譲渡では、対価が大きくなりやすい傾向があり、多くの場合において譲渡所得が発生し課税されることになります。
(2)譲渡収入
譲渡所得の計算の基礎となる譲渡収入は、M&Aにより売り手企業の株主が受け取ることになるM&A株価を指します。このM&A株価は基本的には、買い手側との条件調整により決定されることになります。
企業の株価評価については複数の手法がありますが、日本M&Aセンターが関与する中堅・中小企業のM&Aでは 「時価純資産+営業権」 を基準に決定するケースが多く見られます。
株式価値の考え方

第三者へのM&Aでは、営業権が上乗せされることが少なからず生じるために、いわゆる相続税評価など税務上の株価に比べて高くなる傾向があります。
株式価値に関してはM&Aの企業価値評価(バリュエーション)とは?をご参照ください
(3)取得費
個人の株式譲渡における取得費は、 「実際の取得費」と「譲渡収入×5%」を比較して、有利な方(金額の大きな方)を採用 します。

a.実際の取得費
株式の譲渡所得を求める際に、譲渡収入から控除される取得費は、多くのケースで売り手企業の貸借対照表に記載される 「資本金」と「資本準備金」の合計額 に一致します。
これは、その株主が株式取得のために実際に取得するために出資した資金、「実際の取得費」を表します。オーナー社長が株式を100%保有している場合、この実際の取得費が税金計算上の取得費となるケースが多くみられます。
ただし、過去に創業時の出資額と異なる金額で購入した場合などは、取得費が資本金と資本準備金の合計額に一致しないケースもあるため注意が必要です。
b.譲渡対価×5%
譲渡オーナーが個人の場合は、上記の実際の取得費に代えて、 「譲渡対価×5%」 を用いることもできます。
M&Aによる第三者への譲渡は、株価である譲渡収入が高額になりやすく、この「譲渡対価×5%」が「実際の取得費」を上回るケースも多いので、この比較を忘れないよう注意しておく必要があります。
なお、この「譲渡収入×5%」との比較が可能なのは個人株主のみであり、法人株主の場合は適用されません。
(4)譲渡費用
株式の譲渡所得を求める際に、譲渡対価から控除される譲渡費用には、譲渡側の株主が負担した仲介会社あるいはアドバイザーへの手数料があげられます。
この手数料のうち、着手金についても譲渡側の株主負担であれば、税金計算上は費用として譲渡所得から控除できます。個人株主であれば、これらの費用を消費税込みの金額で譲渡所得から控除することとなります。
| 売り手(個人株主) | |
|---|---|
| 着手金 | 譲渡費用(税込み) |
| 成功報酬 | 譲渡費用(税込み) |
| ※想定するスキームによっては着手金を売り手企業が負担する場合もある |
売り手が留意すべき点(株式譲渡の場合)
株主であるオーナー社長は、売却後に多額の対価を受け取ります。その対価に係る税金がいくらであるか、が最も重要になります。
まずは、株式譲渡において譲渡所得に課される税率について確認します。
前述の通り、個人の株式譲渡に係る税率は20.315 %です。この20.315%は所得税15.315%(復興税率を含む)と住民税5%を合計した税率を指ししています。
この株式譲渡に係る税率は、一律で20.315%であり、他に所得があったとしても、累進課税のように税率が上がることはありません。株式譲渡による所得のみを、給与などの他の所得と分けて税金の計算をすることを分離課税といいます。
所得税は、給与所得等に該当すると累進税率が適用されてしまうため、所得が高額になれば、住民税を含め最大で約56%の税率で課税されます。しかしながら、株式譲渡による税率は一律20.315%です。
M&Aでは対価が多額になるケースが多いですが、株式譲渡であれば他の所得に比べて低い税率で対価の受け取りが可能となると言えます。
株式譲渡による所得の認識時点
(1)認識時点の考え方
株式譲渡に係る税金は、株式を売却した際の譲渡所得に対して課されます。この譲渡所得が認識される時点は、原則的には株式の引渡し日となります。
ただし、特例的に契約の効力発生日としても構わないことになっています。この契約の効力発生日は、単に契約の締結日を指すのではなく、契約の効力が発生する日を指します。
中堅・中小企業のM&Aでは、株式譲渡の契約日から実際に引渡しまでに様々な義務を定めて(クロージング条件といいます)、引渡し日までにそのクロージング条件を満たすことにより、契約の効力が発生することになります。したがって、実務的には株式の引渡し日と契約の効力発生日は同日になります。
(2)認識時点の例
X1年の12月に株式譲渡契約を結んでいたとしても、クロージング条件を満たして株式の引渡しが行われる日が翌年X2年以降になることもあります。その場合は、株式譲渡所得の認識時点も令和X2となります。

譲渡所得に認識時点によって、その譲渡所得に係る税金について確定申告し、納付する年度も変わってきますので留意が必要です。
株式譲渡に係る税金の申告・納付時期
(1)所得税
株式譲渡によって譲渡所得が発生し税金を納める必要がある場合は、どのように税金を納付する必要があるのでしょうか?具体的には、税率20.315%のうち所得税15.315%分の税金を、株式を引渡した日の翌年2月16日から3月15日までに確定申告を提出し、納付する必要があります。この確定申告をした時点で、税務署に納付する必要がある税金はこの所得税15.315%分のみとなります。
(2)住民税
残りの5%分の住民税は、普通徴収か特別徴収のいずれかの納付方法を選択して税金を納める必要があります。
-
普通徴収
普通徴収による場合は、住民税を自分で納付することになります。譲渡所得を認識した年の翌年の6月ごろに通知が届きますので、6月末、8月末、10月末、1月末の4期を納期限に分割して納付する必要があります。もちろん、分割せずに住民税を一括で納付することも可能です。 -
特別徴収
特別徴収による場合は、株式譲渡による所得を認識した年の翌年6月に、給与支払者である会社(特別徴収義務者)を通じて、市町村から本人に通知がきます。そして、その通知がきた6月からその翌年5月までの毎月の給与支払い時に天引きされ、天引きされた住民税は会社が代わって納付します。
買い手が留意すべき点(株式譲渡の場合)
買い手側は、「譲渡時」のみならず「譲渡後」の影響について検討が必要です。具体的に買い手企業で税務が検討されるケースを確認していきましょう。
株式譲渡における税務上の留意点としては、「株式の取得価額として資産計上される価額」があげられます。また、令和3年の税制改正で導入された「中小企業事業再編投資損失準備金制度」の検討が必要となります。
株式の取得価額として資産計上される価額
買い手企業が、M&Aの株式の対価として支払う金額(投資額)は、株式の譲渡価額とDD費用や仲介手数料などの諸経費があります。
(1)株式の譲渡対価
株式譲渡によるM&Aにおいて、買い手企業が売り手企業の株主に株式の譲渡対価として支払った金額は、株式の「取得価額」として資産計上されることになります。
誤解される方も多いですが、株式譲渡によるM&Aでは、税務上ののれんが計上されることはありません。のれんの金額が多額の場合でも、税務上ののれんの償却メリットは取ることはできません。
ここでいう税務上ののれんは連結会計上ののれんとは異なります。
連結会計上ののれんに関しては営業権(のれん)とその計算をご参照ください。
(2)仲介会社への手数料やDD費用などの諸経費
次に、株式譲渡時までに支払う仲介手数料やDD費用などの諸経費の取扱いです。これらの諸経費は以下の図の通りに取扱われます。

この諸経費は仲介手数料の着手金を除き、株式の「取得価額」として資産計上されます。
税務上は、その株式を「取得すると決めた時点以降」の費用は株式の「取得価額」として資産計上する必要があります。基本合意以降に発生する費用がこれに該当します。
したがって、買い手企業において、損金算入することができる費用は仲介会社に支払った着手金のみとなります。株式譲渡スキームを採用する場合、買い手企業がM&Aに伴い支払う諸経費の大部分について損金に算入できない点に留意が必要です。
なお、途中でそのディールがブレイク(案件破談)した場合は、基本合意後に支払う諸経費であっても損金に算入されることとなります。
中小企業事業再編投資損失準備金
令和3年税制改正で導入された「中小企業事業再編投資損失準備金」という制度が、2021年8月からが始まりました。
(1)制度の概要
ざっくりとした制度のイメージは、下記図の通りです。例えば10億円で株式を取得したときに、その期に70%相当の7億円を一括で税務上の損金に算入することが可能となります。
ただし、その損金に算入した70%相当額の金額は、その後、5年間の据え置き期間を経て、6年後から1/5ずつ取り崩す必要があります。この例では1.4億円ずつ税務上の益金(つまり利益)に算入されることとなります。
買い手側としては足元の利益と相殺することで一時的な節税となりますが、6年目から取り崩しがなされるため、単なる課税の繰り延べと言えます。
しかしながら、長期的なタックスプランニングのもと制度の利用ができれば、有効な制度としてM&Aの促進に資すると思われます。

(2)適用要件
この制度を使うためには、株式の取得価額が10億円以下(付随費用を含む)、買い手企業が一定の中小企業(資本金1億円以下。大企業の子会社等は除く)、事前に経営力向上計画の認定が必要、などいくつかの要件があります。詳細については、中小企業庁のHPに手引きの記載がありますので、そちらをご参照ください。
経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について
M&A税務のポイント(事業譲渡の場合)

株式譲渡に次いで採用されることが多い手法が「事業譲渡」です。
事業譲渡は、会社を丸ごと売却する株式譲渡とは異なり、会社の一部の「事業」を譲渡することをいいます。この「事業」とは、その事業を営むために必要な資産のみならず、事業の運営に必要な負債、従業員、契約なども含まれます。
事業譲渡を行った場合、オーナー社長は、会社そのものを売却するわけではありません。取引の主体は会社となり、会社が一部の事業を譲渡することになります。そのためオーナー社長は、事業譲渡後の会社を引き続き保有し続けることが可能です。

事業譲渡では、売り手企業が事業を譲渡して、対価が売り手企業が受け取ることになります。オーナー社長個人が、M&Aによる対価を直接受け取ることはできません。オーナー社長が、事業譲渡によるM&Aによる対価を受け取るためには、その会社から配当や退職金などといった方法に依る必要があります。
事業譲渡の手続き
(1)事業譲渡の移転対象
事業譲渡の手続きでは、売り手企業と買い手企業が事業譲渡契約を結ぶことになります。この事業譲渡では、資産や負債、従業員、契約など事業に必要なものを一つ一つ移転させる手続きが必要です。これを個別承継といいます。
また、その移転する事業によっては許認可が必要な場合もあります。事業譲渡では、許認可を移転させることはできませんので、買い手企業において事前にその許認可を取得する必要があります。
(2)具体的な手続き
この事業譲渡は、求められる会社法上の手続きが少ないため、事業譲渡契約の締結時から譲渡日までの期間が約1カ月程度となる場合が多いです。この期間中に、株主総会決議を行う必要があります。また、資産であれば名義の書換え、負債であれば債権者の同意を得るなどといった手続きが必要となります。
従業員に関しては、事業譲渡で移転する従業員が譲渡の売り手企業に転籍承諾書を提出します。そして、改めて買い手企業と雇用契約を結び直す必要があります。
その他取引先との基本取引契約や不動産の賃貸借契約、その事業を営むために必要な契約関係を、買い手側企業と契約の相手先とで改めて契約をまき直す手続きが必要です。
(3)実務のポイント
事業譲渡は、移転させるモノが多ければ多いほどその手続きが煩雑になってしまうので、移転させるモノを必要最小限に絞ることがポイントです。実務的には移転させる資産については事業に必要な在庫と固定資産程度に抑えます。
負債については事業上必須のものを除き、譲渡対象には含めないことでその手続き負担を軽減させることができます。
もちろん、決算書上記載のない事業運営に必要な契約関係や従業員なども移転させなければなりません。
事業譲渡に係る税金の計算過程
事業譲渡は、譲渡対象会社が有する資産や負債を譲渡することになります。したがって、売り手企業でその譲渡する資産の帳簿上の価額と時価との差額について譲渡損益を認識することになります。
のれん代については、売り手企業と買い手企業との間の条件調整によりその金額が決まります。のれん代として受け取った金額は、すべて売り手企業で譲渡益として認識されることになります。
事業譲渡により発生する譲渡損益は、株主である個人ではなく取引当事者である売り手企業=「法人」において認識されることになります。
事業譲渡による譲渡益は法人の他の損益と通算したうえで所得計算され課税されることとなります。中堅中堅中小企業における法人税等の実効税率は約34%です。
売り手が留意すべき点(事業譲渡の場合)
事業譲渡を行った場合は、売り手企業として税務上どのような点に留意が必要でしょうか?事業譲渡を行った場合は、単に事業譲渡時の売り手企業の課税を考えればいいだけではありません。
事業譲渡のスキームを検討する際には、売り手企業が受け取った事業譲渡の対価を、株主であるオーナー社長へ還流させるまでの税金を考慮しておかなければなりません(事業譲渡対価を売り手企業が活用するケースを除く)。
この節では、事業譲渡における税務上の留意点を解説します。
事業譲渡の実行時の課税
事業譲渡の場合は取引の主体となるのは株主ではなく売り手企業です。そのため、事業譲渡の実行時に課税されるのは、譲渡オーナーではなく売り手企業となります。
中堅・中小企業のM&Aでは、多くのケースで事業譲渡対価に「のれん代」が上乗せされるため対価が多額となる傾向があります。そのため、売り手企業に譲渡益が発生し、法人税等が課されることになります。
事業譲渡に係る「譲渡益」については、退職金を組み合わせて支給することで、退職金支給による「損」をぶつけ、法人税等を圧縮させることができるケースもあります。事業譲渡により課される法人税等については、工夫次第で節税の余地があるといえます。
事業譲渡に係る税率
この事業譲渡時に課される法人税等は、中小企業の実効税率としての「約34%」の税率で課税されることになります。この「約34%」ですが、上述した個人の株式譲渡の場合の税率「20.315%」よりも高い税率であるため、株式譲渡に比べて不利と感じられる方がいるかもしれません。
しかしながら、この記事での詳細は割愛させていただきますが、事業譲渡による譲渡益は、株式譲渡による譲渡所得より小さくなることもあります。
株式譲渡に比べて、課される税率は高くなりますが、税率をかける金額が小さくなることも考慮すると、株式譲渡と事業譲渡のどちらが有利になるかはケースバイケースと言えます。
事業譲渡対価の還流時の課税
(1)売り手企業から株主への対価の還流
上述したように、事業譲渡による対価を受取るのは、株主であるオーナー社長個人ではなく、売り手企業です。オーナー社長個人として手元に現預金が必要な場合は、売り手企業からオーナー社長個人へその対価を支払う必要があります。
したがって、事業譲渡によるM&Aの対価を売り手企業から株主であるオーナー社長に還流する際に、個人の所得として別途課税されてしまうことになります。オーナー社長個人として手取り額を検討する際には、この還流時の課税にも注意が必要です。
(2)対価の還流時の課税
それでは、具体的に売り手企業からオーナー社長個人へ対価を還流する際に、どのような税金が課されるのでしょうか?ここで課される税金は、株主への支払い方法によって変わってくることになります。
支払い方法としては役員報酬や配当、退職金などといった支払い方法があげられます。いずれの支払い方法であっても、売り手企業からオーナー社長個人へ現預金を支払う場合には、税金が課されることになります。
-
役員報酬や配当による支払い
役員報酬や配当で支払った場合には、給与所得・配当所得として総合課税の対象となり累進課税が適用されてしまいます。多額の対価を一度に支払うと税率が最高で約50%以上の税率で税金が課されてしまうため注意が必要です。 -
退職金による支払い
退職金で支給することができれば、税率は最高で約28%で済み、退職所得控除も適用されることになります。そのため、比較的課税が少ない形でオーナー社長への現預金の支払いが可能となります。
買い手側が留意すべき点(事業譲渡の場合)
事業譲渡では、買い手企業は大きく以下の3点について、税務上の検討を進める必要があります。
- 税務上ののれん(資産調整勘定)の取扱い
- 仲介手数料やDD費用などの諸経費の取扱い
- 消費税の課税関係
譲渡後の税務上のれんの取扱いに関しては、金額が多額になるケースも多いですし、消費税についても10%(場合によっては8%)課税されるか、課税されないかではM&A時に支払う投資額も大きく変わることになります。この節では、上記3点について順番に解説していきたいと思います。
税務上ののれん(資産調整勘定)の取扱い
ここでは「税務上ののれん(資産調整勘定)」について解説します。この税務上ののれんは、M&A後に5年間にわたり月割りで損金の額に算入することができるため、買い手企業にとって大きなメリットとなります。この「税務上ののれん」の算定方法は、以下のように算定されます。

事業譲渡では、買い手企業が譲渡対象の資産等を時価で取得することになります。この承継した資産等の時価純資産 を上回る対価を支払った場合には、その時価純資産額を超えて支払った金額が「税務上ののれん(資産調整勘定)」となります。
ケースとしては少ないですが、交付する対価が時価純資産に満たない場合もあります。その場合は、「税務上の負ののれん(負債調整勘定)」を認識することになります。 この「負ののれん」は、「税務上ののれん」とは反対に5年間にわたり月割りで益金に算入、税金計算上の収益となり、法人税等が課税されることになります。
なお、この「税務上ののれん」「税務上の負ののれん」いずれも会計上の処理に関係なく、税務上は5年間で均等に償却しなければならないので注意が必要です。
仲介手数料やDD費用などの諸経費の取扱い
仲介手数料やDD費用などの諸経費については、上述の株式譲渡に比べて取扱いが複雑となります。取扱いをまとめたものが以下の表です。

まず、その支払った諸経費を事業譲渡により取得する各資産の金額(税務上ののれんを含む)に按分します。そして、事業譲渡により取得した資産のうち付随費用として資産の取得価額に含める税務上の規定があるもの(棚卸資産や有形固定資産など)に按分された費用については、その資産に取得価額に含めて資産計上する必要があります。
事業譲渡により取得した資産のうち付随費用として資産計上する規定のないもの(売掛金等の金銭債権や税務上ののれんなど)に対応する費用については、資産計上する必要はなく、損金に算入することができます。
このように株式譲渡とは違い、「取得の意思決定以降」の費用を全て資産計上するわけではありません。資産計上する金額と損金の額に算入することができる金額に分けて取扱う必要があります。
なお、この事業譲渡に係る諸経費については、資産計上する必要はなく、諸経費の全額を損金の額に算入できるとする見解もあります。
消費税の取扱い
(1)消費税の事前検討
事業譲渡を行う際の消費税の課税関係について確認します。事業譲渡は資産等の個別承継に該当することになります。事業運営に必要な資産等を個別に資産等を売買するイメージです。
譲渡対象資産に、例えば在庫や建物など消費税の課税対象資産に該当するものがある場合には、消費税10%(軽減税率が適用されるものは8%分)の金額を支払わなければなりません。
また、「営業権」についても消費税の課税対象となる点には注意が必要です。この「営業権」については、案件によっては多額になりますので、その10%分の消費税も相応の金額になる可能性があります。あらかじめM&Aの投資額として考慮しておかなければ、思わぬ金額を追加で支払わねばならないことになります。
例えば、事業譲渡の対価として1億円の「営業権」を上乗せして支払う場合は、実際には消費税分を含めて1億1千万円をM&Aの投資額として考慮する必要があります。
買い手企業の資金状況によっては、金融機関から融資を受けてM&Aを実行するケースも想定されます。消費税の検討を忘れたまま商談を進めてしまうと、思わぬ追加融資が必要となってしまい、最悪のケースではディールのブレイクにも繋がりかねません。事業譲渡では、検討の初期段階から消費税を考慮することが大切です。
(2)仕入税額控除
なお、この事業譲渡時に支払った消費税ですが、その後の消費税の計算において、買い手企業が支払う消費税から控除されることになります。これを仕入税額控除と言います。
この控除される消費税の金額は、会社の業態や採用している消費税の計算方法によっても変わってきますので、あらかじめ顧問の税理士先生との相談しておくことが望ましいです。
M&A税務のポイント(退職金について)

上述の株式譲渡と組み合わせる形で、売り手企業の役員がM&Aを機に退職する場合「退職金の支給」を検討するケースが多く見られます。この節では、その退職金の基本的な概要、手続き、退職金に係る税金の計算過程を簡単に説明します。
退職金の概要
(1)退職金の性質
中堅・中小企業のM&Aでは、M&A時に売り手企業のオーナー社長が退任するケースが見られます。
もちろん、社長や会長など継続して会社に残られるオーナー様も多くいらっしゃいますが、事業承継を目的とするM&Aの多くケースでは、M&A時にオーナー社長は退任し、その後は顧問として一定期間の引継ぎをされることになります。
こうした場合、役員の退任時に「役員退職金の支給」の検討が行われます。
退職金には以下のような性質があります。
- 過去の勤務に対する賃金の後払い
- 在職中の功労に対する報償
- 退職後の生活保障
そのため、他の給与所得などに比べて税率や計算過程において税制上優遇されています。そのため、この退職金が手取り額を最大化させるうえで、この退職金の活用が重要となります。
(2)株価への影響
役員退職金の支給を前提とすることで最終的なM&A株価に影響が生じます。退職金を支給することで、当初のM&Aの対価の一部が株式譲渡の対価としてではなく役員退職金に置き換わるイメージです。
買い手側にとっては投資額を低く抑えることにつながるので、実務上、株価について折り合わない時に、退職金で調整をつけることがあります。
株式価値の考え方

(3)株主以外の役員にも対価の支払いが可能
役員退職金は、退職した役員に対して支払う性質のものです。そのため、株主であるオーナー社長のみならず、オーナー社長の奥さんや子供などの親族が役員になって業務に従事しているケースであれば、それらの役員となっている親族にも退職金としてM&Aの対価を支払うことが多く行われています。
これを利用すればM&Aの対価を単純に株式の持分比率で按分するのではなく、特定の人物(退任する役員)に対価を寄せるといったことも可能となります。
退職金支給の手続き
(1)支給のための手続き
役員退職金を支給するには、定款に定めていない場合、株主総会において支給の可否、支給方法、支給金額などの決議が必要となります。しかし、実際には株主総会で取締役会に一任する旨の決議が行われることが多いです。この役員退職金の支給を決議した株主総会や取締役会の議事録は、必ず保存しなければなりません。
中堅中小企業のM&Aにおいては、最終契約で役員退職金の支給を定め、株式の譲渡日後に買い手側の義務として退任した役員に退職金を支給することになります。
(2)役員退職金規程の有無
役員退職金の金額は、会社で作成されている役員退職金規程をもとに決められることになります。しかしながら、中堅中小企業では役員退職金規程を作成していない会社も非常に多く見受けられます。
役員退職金を譲渡会社において損金算入するためには、必ずしもこの役員退職金規程を作成する必要はありません。しかしながら、規程を作成したうえで、規程に従った金額を支給した方が、後々の税務調査などで算定方法や金額の客観性を積極的に説明できるため望ましいと考えられます。
退職金の支給額と税金の計算過程
(1)功績倍率法による支給金額
まず、役員退職金は、退職金を支給した売り手企業において税務上の適正金額を損金として処理することができます。この適正金額は、明確に定めた税法上の規定が存在しておりませんが、一般的には判例等の過去実績に基づいた功績倍率法と呼ばれる手法で退職金の支給金額を算出することが多く行われています。

(2)最終月額報酬について
最終報酬月額は、基本的に退任される役員の方の退任直前の月額報酬を指します。しかし、最近ではコロナによる業績不振のため、役員報酬を減額しているケースも見受けられます。
そういった場合には、「最終報酬月額」に代えて「適正報酬月額」をもとに役員退職金の支給額を検討することもあります。この「適正報酬月額」には、業績不振による減額前の役員報酬や直近数年の役員報酬を平均した金額を用いることになります。
なお、役員報酬を多額支給するために、退任直前に役員報酬を増額させればいいのではないか?と考える方も中にはいらっしゃいます。しかしながら、退職金を多く支給させることだけを目的として、一時的に役員報酬を増額させた場合は役員退職金の過大支給となり、税務リスクとなるため注意が必要です。
もちろん、会社業績への貢献度の高さなど正当な理由があれば、役員報酬を増額させたとしても問題はありません。
(3)功績倍率の検討
功績倍率についてはその妥当性の判断が難しく、議論になる部分ではありますが、実務的には以下の倍率が基準として一般的に用いられています。
【一般的な効率倍率】
- 代表取締役 → 3倍まで
- 取締役 → 2倍まで
- 監査役 → 1.5倍まで
この功績倍率は、退職の事情や、その法人に従事した期間、その会社に類似する同規模で同業の退職金をもとに決定されることになりますので、退職金の支給を実際に検討する際には顧問の税理士先生に相談が必要となります。
(4)退職所得控除
上記の算式の通り、まず退職所得から退職所得控除が退職金から控除されます。退職所得控除の算定式は以下の通りです。
【退職金所得控除】
1:勤続期間20年以下
40万円×勤続年数(最低80万円)
2:勤続年数20年超
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数は1年未満を切り上げた年数
退職金を支給しても、この退職金所得控除までの金額であれば税金はかかりません。退職所得控除については、その勤続年数が長ければ長いほど金額が大きくなるため、より税制上の優遇を受けることができます。
(5)退職金に対する実質税率
退職所得控除後の金額に「1/2」を乗じて、退職所得を算出することになります。本来、所得税等の税率は最大で約56%(所得税の他、復興税と住民税を加味した場合の最高税率)ですが、この1/2をかけることで*実質税率がその半分の約28%*と考えることができ、結果的に退職金に係る税金が圧縮されることになります。

ここで注意が必要なのが、勤続年数が5年以下の役員へ退職金を支給する場合には、この「×1/2」を適用できない点です。したがって、役員に就任したばかりの方に支給する場合には、最大で約56%の税率で税金が課されてしまい十分なメリットを享受できない点に留意が必要です。
(6)分離課税
また、この「退職所得」については、「分離課税」として税金を計算することになります。分離課税は、退職金を他の所得と分けて税金を計算することができることを指します。給与所得や配当所得、不動産所得などの退職金以外の所得があったとしても、退職金のみで所得税等を計算することになります。
売り手が留意すべき点(退職金について)
これまで述べたように、中堅・中小企業のM&Aではどのスキームを採用する場合であっても、退職金の支給を考慮・検討するケースが多く見られます。
ここでは退職金の支給に係る税務上の留意点を、退職金を受け取る「オーナー社長個人」と「売り手企業」に分けて解説します。
退職金を受け取るオーナー社長個人の留意点
(1)退職金に課される税率
退任することとなるオーナー社長個人が、売り手企業から受け取った退職金は、オーナー社長個人の税金計算上は「退職所得」として課税されます。そのため、上述のように個人として受け取る退職金は、最高税率が約28%と税率面で優遇されています。
(2)手取額の最大化
退職金は累進税率が適用されるため、退職金の金額次第では、株式譲渡に係る税率よりも低い税率で退職金の支給が可能です。これに加えて退職所得控除も適用されます。
退職金の支給額によっては、単純に株式譲渡だけで対価を受け取るよりも譲渡側の手取額が大きくなる可能性があります。

(3)退職金に係る税金の納税
● 「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合
売り手企業からオーナー社長に退職金が支払われる際に、所得税等が源泉徴収されます。退職の際にオーナー社長が「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、退職所得の金額に応じた適正な税額で源泉徴収されるため、確定申告をする必要はありません。
● 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しない場合には、簡便的に所得税が20.42%で源泉徴収されることになります。その場合は後日、適正な税額になるようオーナー社長自身で確定申告を行い、概算で行われた源泉徴収税額の精算を行う必要があります。
退職金を支払う売り手企業の留意点
次に、退職金を支払う売り手企業における税務上の留意点です。退職金は、支払った売り手企業で損金として、税金計算上の費用として計上することができます。
ただし、オーナー社長個人に支払った金額が無制限に損金算入されるわけではありません。あまりにも高額な金額を退職金として支払ってしまうと、課税当局に否認されてしまうリスクがあるので注意が必要です。
退職金が高額かどうかの基準は、一般的に前述の功績倍率法に基づいて判断することになります。実務的には、功績倍率法で算出された金額までであれば、損金算入できるものとして取り扱うことが一般的ですが、実際に退職金の支給を検討する際は、事前に顧問の税理士先生に相談することが望ましいといえます。
買い手が留意すべき点(退職金について)
M&Aの際に、売り手企業から退任するオーナー社長に退職金を支給することで、買い手企業では基本的に以下のようなメリットがあると考えられます。
- 退職金を税務上の適正額で支給する場合、 損金の額に算入する ことができる
- M&Aの株価を減額する結果となるため、 投資額を圧縮する ことができる
この節では、これらの退職金支給による買い手企業のメリットについて解説していきたいと思います。
退職金の支給による損金算入
(1)退職金の損金算入メリット
役員に支給した退職金は、税務上の適正額であれば損金の額に算入することができます。これまで、その売り手企業の成長に貢献してきたオーナー社長には、多額の退職金が支払われるケースも少なくありません。この退職金は一般的には、功績倍率法による限度額の範囲内で損金に算入することができます。
(2)退職金による損金のインパクト
多額の退職金を損金の額に算入することができるので、退職金を支給した年の売り手企業の法人税等を減少させることに繋がります。退職金を支給した年で、退職金による「損」を使い切ることができない場合は、繰越欠損金として10年間にわたりその「損」を使用することが可能です。
(3)その他の留意点
多額に損金を計上できる役員退職金ですが、支給する金額によっては売り手企業が債務超過になってしまうケースもあります。売り手企業が債務超過になることで、許認可やビジネス面に影響を及ぼさないかは、税務上の観点とは別に検討しなければならないので注意が必要です。
なお、この損金算入メリットを享受したいにも関わらず、売り手企業に現預金がない場合もあります。実務上は、買い手企業が売り手企業に現預金を貸付け、その現預金でオーナー社長に退職金を支払ったりするケースもあります。
退職金の支給による投資額の圧縮
基本的に、オーナー社長の退職金を控除する前の時価純資産を基準にM&Aの株価は検討されることになります。
退任するオーナー社長は、条件調整で決まった金額を株式の対価で受け取るか、退職金で受け取るかのいずれかとなります。この株式譲渡の対価と退職金支給による対価は、それぞれ支払元が異なることになります。

株式譲渡としてのM&A対価は、買い手企業が対価をオーナー社長に支払うことになります。一方、退職金としてのM&A対価は、売り手企業から支払われることになります。退職金として支払われる分は、買い手企業から支払う必要がないので結果として投資額が圧縮されることとなります。
M&Aではその対価が高額となるケースが多く、その場合は買い手企業が金融機関からの融資を必要となることも多々あります。
退職金を支給することで、投資額を圧縮することができれば、買い手企業としてはM&Aにより売り手企業を買いやすくなるといえるのではないでしょうか。
M&A当事者にとって、税務の知識は不可欠
中堅・中小企業のM&A税務の知識を知っているか否かで、譲渡側では最終的な手取り金額が大きく変わってくることになります。また、買い手側においても事業を継続していく中で、税務コストの検討を行うことは非常に重要です。
本記事をご覧いただき、中堅・中小企業のM&A税務の概要のイメージがつきましたら幸いです。実際には高い専門性・経験が要求されてくることになるため、経験・実績豊富なM&Aの専門会社にご相談いただくことをお勧めいたします。
専門的な会計・税務のご相談は、税理士法人MAable(マーブル)まで











