「事務所をより大きくしていきたい」。あえて変えることを宣言し、PMIにも注力

譲受け企業情報
-
- 社名:
- 社会保険労務士法人M&パートナーズ(静岡県)
-
- 事業内容:
- 社会保険・労働保険手続き等
-
- 売上高:
- 約1.2億円(2023年12月期)
- 従業員数:
- 16名(パート含む)
※M&A実行当時の情報
※情報は前身の松澤社会保険労務士事務所のもの
M&パートナーズは、静岡県浜松市で40年以上にわたり人事・労務サービスを提供してきた社会保険労務士事務所です。関東エリアの顧客増加を受け、2024年10月に東京の社会保険労務士事務所であるやさか事務所との吸収合併を行いました。初めてのPMIに取り組む松澤浩貴代表に、今回のM&Aによる長期的な成長戦略についてお聞きしました。(取材日:2025年2月4日)
譲渡企業インタビューはこちら
関東エリアの顧客増加に伴い現地に拠点をもつためM&Aを検討
――はじめに、M&パートナーズの業務内容や強みを教えてください。
譲受け企業 M&パートナーズ 松澤様: 静岡県浜松市に事務所を構える社会保険労務士法人として、1982年の設立以来、40年以上にわたり幅広い人事、労務サービスを提供しています。社労士事務所の多くは1人、2人の規模が多いですが、当事務所は16人のスタッフを抱え、業界の中では中規模事務所と位置づけられています。2015年に父母から当時3,200万円の売上げ規模だった事務所代表を引き継ぎ、M&Aの実行に合わせて2024年には法人化も実現しました。
当事務所の特徴は、DX化の大きな流れが労務の領域においても避けられないと予測し、早期にIT化に着手してきたことです。業界の中でいち早く業務効率化や付加価値の提案が実現可能となり、今ではITに強い社会保険労務士事務所として大きな強みとなっています。
私自身が一貫して大切にしてきたのは、従業員やお客様、関係するすべての方との信頼関係を築くことです。法人化に際して社名に「パートナーズ」という言葉を入れたのも、その強い気持ちを込めたかったからです。おかげさまで顧問先の数も着実に増えていますが、日々の仕事において丁寧かつ迅速なコミュニケーションを取るといった基本的な部分を疎かにせず、真摯に向き合うことを常に大事にしています。継続的な信頼関係を築くために始めたメルマガも8年目を迎え、顧問契約を結んでいるお客様に対して毎月1回、お役立ち情報を発信し続けています。
――M&Aによる譲受けの検討を始めたきっかけは何だったのでしょうか?
松澤様: 背景には、新型コロナの感染拡大を契機に、東海エリアに加えて関東圏の顧問先が一気に増えたことがあります。これまでも関東のお客様をご紹介いただくことはありましたが、距離的な制約を乗り越えられず、なかなかご縁につながりませんでした。ところがコロナ禍では一転、リモートが主流に切り替わったことが追い風となりました。地理的な距離がデメリットではなくなったわけです。
しかし、コロナ禍が落ち着くと徐々に対面での活動に戻り、再び距離が大きな問題となってきました。関東圏の顧問先が40件程度にまで拡大したこともあり、東京に拠点をもつ必要性を強く感じるようになりました。

絶好のタイミングで提案を受けトップ面談から4カ月で成約
――具体的にM&Aに向けてどのように動かれたのでしょうか?
松澤様: 日本M&Aセンターを含む複数のM&A仲介会社に希望条件をお伝えしていましたが、2024年のはじめに事務所を移転したため、しばらくはそれどころではありませんでした。ようやく移転が終わり落ち着いたのが2024年2月、その絶好のタイミングで連絡をくれたのが日本M&Aセンターでした。
東京の社会保険労務士法人について提案を受け、秘密保持契約締結後すぐに情報開示をしてもらい、その後、さすがのスピード感でトップ面談の場が設定されました。着手金が発生すると聞いて一瞬迷いましたが、タイミング的にフレッシュな気持ちだったため、「ここは勢いに乗ってみよう」とお会いすることにしました。
――やさか事務所の池上代表とお会いして、どのような点に魅力を感じましたか?
松澤様: 池上代表は社労士として長い経験と実績をお持ちで、社労士としてはもちろん経営者としても信頼できる方だと感じました。当初は4、5人規模の事務所を考えていたのに対して、やさか事務所はスタッフ11人でしたが、規模の大きい事務所のほうがよりベストだと考えました。顧問先の数も十分で、勤続年数の長いベテランスタッフも何人かいて、バランスの取れた事務所だと感じました。また、当事務所のノウハウを活かして新たな付加価値提案を行うことで、より収益が増える可能性がある点も魅力でした。
――M&Aの検討期間中に法人化されましたね。
松澤様: 検討当時は松澤社会保険労務士事務所という個人事務所でした。法人化については近々に取り組もうとは考えていませんでしたが、やさか事務所が法人であるため、このM&Aを実現するには法人化が必須条件であることがわかりました。事務所の移転に伴う諸手続きがようやく終わったばかりで、法人化となると従業員にさらなる負担をかけることになります。迷いはありましたが、M&Aはタイミングやご縁が大事だと強く感じていましたので、ここはやるしかないと決断しました。スピード感をもって対応し、結果、トップ面談からわずか4カ月で成約までたどり着くことができました。
――今回のM&Aについて、M&パートナーズの従業員の皆さんの反応はいかがでしたか?
松澤様: 「事務所をより大きくしていきたい」という考えは以前から伝えていましたし、規模が大きくなることは働く側にとってプラスになります。ありがたいことに、みんな好意的に受け止めてくれました。

強固な信頼関係を築くため、あえて「変わります」と宣言
――PMI(M&A後の統合プロセス)にはどのように取り組まれていますか?
松澤様: 吸収合併後1年間は池上代表に残っていただくことが条件なので、当初はすぐに何かを変えず、1年かけてゆっくり融合していけば良いと考えていました。ところが、日々の仕事内容はこれまでと変わらないとはいえ、やさか事務所の従業員の皆さんは相当不安に感じているのがわかりました。代表が変われば当然考え方が違いますから、やり方も変わってきます。「変わらない」というのは嘘になります。従業員との信頼関係をしっかりと築くためには、ここはスピード感をもって最初に変えてしまったほうが良いだろうと考えを改めました。
そこで「色々と変わります」と早々に宣言しました。ただ、もちろんそれは良いほうに変えるという意味なので、「皆さんの意見を聞きながら、マイナス面をできるだけプラスに変えていきます」と伝えました。それには従業員とのコミュニケーションをしっかりと取ることが重要ですので、月の半分は東京の事務所にいるようにしています。
最初に着手したのは、もっとも重要な給与体系です。士業で導入されることが多い固定残業制を廃止し、残業部分を透明化して不公平感をなくしたほか、賞与も最低保証の基本部分に業績連動でプラス加算する体系に移行するなど、抜本的に見直しました。
また、東京事務所にもITシステムを導入して業務効率化を図るとともに、クラウドを活用して浜松事務所と情報共有できる仕組みを整えました。不明点は東京と浜松のスタッフ間でコミュニケーションを取り、スピーディーに解決できる体制を構築しています。
PMIについてはのんびり進めようと考えていましたが、予期せぬ課題に直面し、当初の想定より苦労しています。ただ、浜松事務所のほうは従業員が育ち、ベテラン勢が基盤となって安定しているので、浜松と東京でうまくバランスを取りながら進めているところです。
息子の代になったときのことまで考えて、M&Aを決断できた
――今後の成長ビジョンを教えてください。
松澤様: 社会保険労務士の仕事は個人で行うことが多く、組織化するのはなかなか難しい業界ではありますが、長期的には50人規模の社会保険労務士法人にまで拡大し、売上3億円を目指していきます。
――日本M&Aセンターに対する評価はいかがでしょうか?
松澤様: 日本M&Aセンターは他社と比べてやはりレベルが違うと感じることが多いです。M&Aはこれまでの実績、経験、ノウハウの豊富さが重要な要素だと思います。その点で、日本M&Aセンターには圧倒的な安心感があります。
――ご経験を踏まえて、M&Aを検討する経営者や士業の皆さんに向けてメッセージをお願いします。
松澤様: ここから10年先、20年先にどうなっていたいかを長期的視点で考えた時に、選択肢の一つとしてM&Aがあるのかなと思います。私自身、息子の代になったときのことまで考えてはじめて踏ん切りがついたところがあります。短期間で儲かるかどうかという視点でM&Aを考えるのは本質ではないと考えます。
また、士業においては特に人がすべてと言っても過言ではありません。経験値の高い従業員が一定数いなければ仕事は回りませんので、勤続年数の長い従業員がどれくらいいるかは、相手企業を決める上で非常に重要なポイントです。従業員規模と有資格者の数だけで判断するのではなく、組織規模に見合ったスキルを持った人員構成になっているかを判断することが大切だとお伝えしたいです。
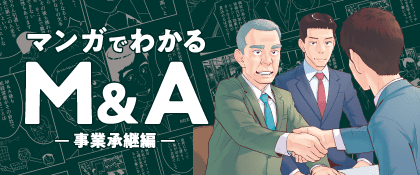
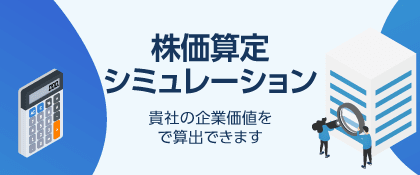


-

※役職は取材時コンサルタント戦略営業部 東日本2部 田中 樹(社会保険労務士法人M&パートナーズ担当)
組織としてさらなる成長・拡大を目指される中で、商圏の補完といったシナジーがあり、双方の存続・発展につながる素晴らしいマッチングが実現できたと思います。譲り受けるにあたって、法人化をして屋号を「社会保険労務士法人M&パートナーズ」に変更するなど、事業の大きな転換の契機にもなりました。初回のトップ面談時に、同じ社会保険労務士同士だからこそ通じる苦労話で盛り上がり、今後のビジョンについて生き生きとお話しされる姿が印象的でした。